1/11(土)17:00~ Skyシアター MBS

スタッフ
上演台本・演出 ケラリーノ・サンドロヴィッチ
美術 松井 るみ
照明 関口 裕二
音響 水越 佳一
衣装 安野 ともこ
ヘアメイク 宮内 宏明
ステージング 小野寺 修二
キャスト
ラネーフスカヤ夫人 天海祐希
トロフィーモフ 井上芳雄
アーニャ 大原櫻子
シャルロッタ 緒川たまき
ワーリャ 峯村リエ
ドゥニャーシャ 池谷のぶえ
ロパーヒン 荒川良々
ヤーシャ 鈴木浩介
エピホードフ 山中崇
ピーシチク 藤田秀世
ガーエフ 山崎一
フィールス 浅野和之
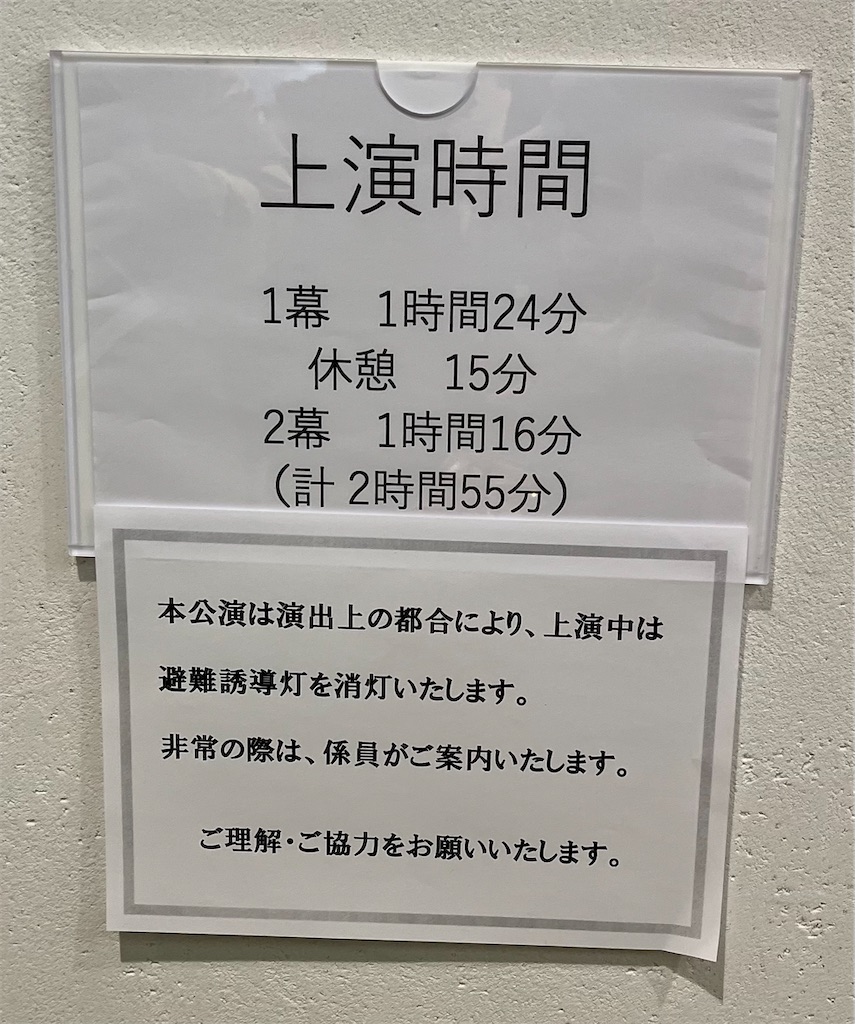
KERAさんが「チェーホフの4大戯曲」を演出する、という試みの最終章のみの観劇で、かつ、初「桜の園」でした。
前知識なしでNTLiveの「かもめ」
を見たとき、演出が斬新すぎて初心者にはかなり分かりにくい作りだったので、戯曲を読んでから見に行こうかと思っていたのですが、シスカンパニーのインスタアカウントで井上芳雄さんの
「どうなるんでしょう。ご存じの方も多いと思います。名作だから!」とのお言葉を聞いて、「名作なのに知らない」のは逆に少数派なのかも、KERAさんも「奇をてらわず作る」とおっしゃっていたし、ここは「せっかくあらすじを知らないのだから、このままの状態で、どうなるかドキドキしながら見よう」と思いなおして、なるべく無の状態で劇場に赴きました。
なので、お話し的にはやっぱり3幕終盤が「そうか、そうくるのか!」みたいな驚きがあって、そしてやっぱりラストシーンに、何というか、変なのですけれど「ああ、よかったね。あのお家に最後まで寄り添ってくれる人がいてよかったね」みたいな感想を抱きました。
劇中で「ロシアの農奴解放」の話題が登場するのですが、このことについて私は全く知らなくて、でも知らなくてもその「農奴解放」で今、この劇にいるロパーヒンがある、ことはちゃんと分かりましたし、そういう時代の変わり目に、変わった者、変われない者、未来に期待している者、なんとなくそのまま生きている者が混在していて、それが今現在とも重なりあうような気がして、非常に興味深かったです。
幕間にプログラムのチェーホフの生い立ち解説を読んでしまったので、ロパーヒンが勝手にチェーホフと重なるように見えてしまったのですが、改めて終演後プログラムを読み、戯曲を読むと、ロパーヒンをああいう人として演出してあったせいなのかなとも思いました。
確かにロパーヒンを悪役っぽく演出することも演じることも可能で、それはそれでどういう印象の作品に見えるのか興味があるのですが、今回は百姓の息子だった人物が「農奴解放」を経て実業家になった、という真っすぐな描き方で、「百姓の息子」時代に、階級の違う「貴族の奥様(ラネーフスカヤ夫人)」が優しくしてくれたことがずっと心の中にあって、だからこそ一所懸命に夫人に「桜の園」を手放さない方法を提案し続ける一方で、最終決定の際に感情が高ぶっていったのだろう、と想像できる人物で、荒川さんがそういう人らしい人を好演されていたなと、戯曲を読んだ後に改めて感じたりしました。
一方で「貴族の奥様」であるラネーフスカヤ夫人は、私の想像の中の「貴族の奥様」らしくないなとも感じました。個人的にはかつて裕福だった気さくな奥様くらいの感じで、「貴族」という血統には一切こだわっていなくて、「世間知らずのお嬢様」のまま大人になったような人物なのも興味深かったです。
トルストイの「アンナ・カレーニナ」が本当に貴族の奥方で温室のバラで、初めての恋に浮かされて飛び出した温室の外では生きられなかったことを思うと、パリでもそれなりに生きてきたラネーフスカヤ夫人には割と共感してしまったのです。
あの浪費の仕方とか、難しいことは無意識的に考えず、思考回路に入らない感じとか見ていると思い当たる節がありすぎて、反省しましたよ…。
(就職超氷河期世代なので、定年まで勤め上げて、老後は年金で優雅に暮らせる、なんてことは思ってなかったですけど、定年がどんどん引き上げられ、年金ももらえるかどうかも分からず、でも医療が発達して人生100年時代になるから、資産運用とかして自分でなんとかしろって言われても、もう分からないの、聞きたくない、考えたくない、というこの気持ちと一緒にしてはいけないけれど、感情としては近しいものはあると思うんです...。)
多分、演出家の数だけ、そして演じる人の数だけ、それぞれに魅力的なラネーフスカヤ夫人があると思うのですが、今回の天海祐希さんはとにかく「お美しい奥様」と呼び掛けられるのが本当にぴったりで、ワーリャ役の峯村リエさんとともに長身で、美しいドレスが映えるのがとてもステキでした。
本当衣装がどれもシックなのに素材が上質で、それを美しく着こなす天海祐希さんは眼福以外の何物でもなかったです。
なのに、どこか親しみやすさがある、という点では、今回の演出の中での天海祐希さん、という選択はぴったりで、というか、天海さんのラネーフスカヤ夫人をこういう風に演出されたKERAさんがやっぱりすごいな、と思うのです。
その美しさを際立たせた天海さんに対して、真逆に仕掛けられたのが井上芳雄さんのトロフィーモフなのかなと思います。「容姿いじり」はどうなのか、という感想を見かけたのですが、戯曲にもそのまま台詞に書かれていました。もしこれをKERAさんが分かりやすいように書いた言葉であったなら問題かもしれないけれど、見ているときに私が思ったのは、トロフィーモフはそれこそいち早く「見た目で判断されること」を一つの人間の抱える問題として捉えて、敢えて容姿を整えなかったのだ、ということでした。
となると、もちろん登場人物はなんか尊大なトロフィーモフへの嫌味を含んだりしながら使っていたりするけれど、多分に発せられる「ハゲ」という言葉に反応して笑う方に無意識の見下した視線があり、もちろん私もやっぱり台詞の応酬の中で笑ってしまった部分もあって、「ルッキズムって難しい」とつくづく感じました。あの芝居の登場人物の中で、トロフィーモフだけはラネーフスカヤ夫人のことを美しいと讃えるところもないことを思うと、やはり彼は「ルッキズム」を意識していて、それを伝えるツールとしての「容姿いじり」だと思ったので、個人的には全てこれを消してしまうとトロフィーモフの問題意識が1つなくなって見えるので、このままでいいのではと思います。
井上芳雄さんから漂う知性や品が活かされつつ、いい感じに鼻につくところ(ご本人がパブリック・イメージとして特にトーク番組とかで出されている部分)が、なんというかぴったりで、驚くほどハマり役だったと私は思いました。
そのトロフィーモフとともに、新しい時代を生きる者として描かれた娘のアーニャ。
4幕の
あたしたちの前に、新しい、目にしたこともない世界が開けてくるんだわ。
(浦 雅春訳)
と母親のラネーフスカヤ夫人に語りかける部分(すみません、劇中ではどういう言い回しだったかは覚えていないです…)なんかは、「ヘアスプレー」の「Welcome To the 60's」とかをも彷彿させて軽やかで生命力に満ちていました。
ただアーニャのこの言葉も母親には届かないし、アーニャも伝えようとはしていない。登場人物が会話しているようで、コミュニケーションを取ろうとしていない、のは、私が唯一、事前に勉強していたチェーホフの短編「魔女」なんかにも共通していて興味深く、今回のこの作品は本当にチェーホフの入り口として、とてもよく作られていたのではと感じています。
キャストの皆さん本当に素晴らしくて、一人一人に印象的なシーンがあるのですが、書き出すと長くなるので、お一人だけ最後にあげるなら、今回はやはり私は池谷のぶえさんのドゥニャーシャでした。いや本当に驚きました。オペラグラスで覗くまでは若い俳優さんと信じて疑っていなかったくらい、本当に20代くらいの女性に見えました。オペラグラスで覗くと池谷のぶえさんだと分かるけれど、それでも20代くらいの女性に見えるんですよ!めちゃくちゃチャーミングでかわいくて、本当、俳優さんってすごい!
ところで、一歩踏み出せば物につまずいたり、新しい靴を買えば不良品だったりするエピホードフを「不幸の吸い取り紙」と劇中では表現していましたが、私が購入した戯曲本では「二十二の不仕合せ」と書かれてあって、注釈が掲載されていました。注釈がないと理解できない言葉はちゃんと変えられている、こういうのも「上演台本」の意義なんですね。
そう思うと過去3作を見られていないのが今さらながら残念なのですが、せめてこの作品は見られてよかったなと思いますし、衣装や照明は好きだったけれど、若干セットには不満があったので、今後それこそNTLiveとかで斬新な演出の「桜の園」が上映された際にはいそいそと見に行きたいと思っています。
ところでこの作品が「悲劇か喜劇か」問題なのですが、何を笑えるかは結構国民性が出る気がしているのです。
エジンバラ・フリンジ・フェルティバルに参加しているとき、ジーン・ブリューワー自身が脚本を書いた「K-PAX」とサルトル「出口なし」、ゴーゴリ「狂人日記」の3本に音響照明スタッフとして関わっていたのですが(ちなみに演出は全てロシア人、役者は英国人、スペイン人、ロシア人、ベルギー人、ノルウェー人、コソボ出身者でした)、特にゴーゴリ「狂人日記」を完全に喜劇ととらえている欧米の観客が多いようで割と爆笑の日が多かったのです。でも私は主人公が少しずつ狂っていく様子の何が面白いのかさっぱり理解できず、笑いのツボの違いを実感して終わった記憶があります。だから「桜の園」のどのあたりを「喜劇」と捉えているかは、ロシアの人に聞いてみないと分からないような気がするのです。
もちろん、「桜の園」の中で繰り返されるコミュニケーション不全のやり取りや、人物のあり方に面白みはもちろん感じるし、その滑稽さを笑えるところもあるのですが、今の日本人にとってこれを喜劇や笑劇ととらえるのはなかなか難しいかもしれない、と思っています。
ただ描かれているのは多分、もっと時代が変わっても変わらない人間の生き様だと思うし、3幕のロパーヒンの衝撃から、1幕冒頭をふっと思い出させる作りとかもやはり上手いし、名作であることは間違いないので、今後もいろいろなパターンで見られることを願っています。
最後にどうでもいいかもしれない違和感を1つ。
KERAさんの公演のプログラムの手触りが普通のマットコートだ!
てことでした笑
シスカンパニーのバックアップは素晴らしいけれど、KERAさんのプログラムのこだわりは反映されないんだなあと変なところに反応してしまいました。
